2025.07.07
グラフィックデザイン学科

思ったより早く梅雨が明けてしまいました.7月の頭ならまだ梅雨の中,曇り空の中で会場を回れるかも,と期待していたのに,灼熱のEXPO体験となりました.
今回は「デザイン」の視点で万博で感じたことを学びのコンテンツとしてまとめていきます.
1.会場構成とパビリオン
2.全体のデザインシステム
3.グッズ
それでは,さっそく参りましょう.
| テーマは「デザイン」 | 大阪関西万博のテーマをご存じでしょうか?「いのち輝く未来社会のデザイン」がそのテーマです. 要約すると「いのち」を繋ぐ「みらい」をどう「デザイン」できるか,ということなんです.ここにまず「デザイン」という言葉が出てきています.この意味することは何でしょう?そこに,現代社会の中の「デザイン」の存在意義があります.それだけ「デザイン」が社会で必要とされている,という表われです. |
|---|---|
| コンセプトは「未来社会の実験場」 | さらに噛み砕くと,世界の課題を共有し,一緒に解決するためにみんなで考えてアイデアを創造し発信しよう,ということのようです.ここでは「課題」を「共有」し「共創」で解決していこう,という「共につくる」ということが中心に添えられています. |
| そこから見えてくること. | 複雑化する社会の中で,より良い未来をつくるためには「共につくる」ことが必要.そして複雑なテーマを他者と共創するときに大事になってくるのが「デザイン」という多様性を束ねるための「流れ/方向性」を生み出す力なんです. いま,デザインが未来の社会を導く存在なのです. |
| デザインは希望である | 世界80億人ひとりひとりの「いのち」を考えるとき,ひとつとして粗末に扱われていいものは無いはずですよね.しかし残念ながらまだまだ世界は問題が山積みです. そんな中でも,明日はきっと,と誰しも幸せを願うはず.それはたとえ苦しみの中でも,戦火の中であっても. デザインは明日を考えること.つまり,デザインは希望なのです. |

まずは入場前の動線をどう捌くか,というところから会場のデザインは始まります.夢洲駅から,野球のスタジアムがまるまるひとつすっぽり収まるほどの広場がゲート前に設けられています.
写真に写っている日傘は,入場前の列に並ぶ人のために無料で貸し出される仕組みになっています.季節に応じた臨機応変なオペレーションを感じます.

ご存じ大屋根リング.世界最大の木造建築となりました.設計は日本を代表する建築家 藤本壮介氏.実際に体験してみると,壮大なスケール感に思わず「おお」と声が出ます.しかし,不思議と威圧感がないんです.壁がないことが大きな理由だと思いますが,こんなに巨大なのに人が安心して招き入れられる懐の深さは,ゆとりある大きさと木材の安心感というか親密感なのでしょうか.不思議な建築です.

リングの中を上から見る.直射日光を避けて多くの人が行き来します.ベンチはもちろん,自動販売機や給水機,ゴミ箱なども適宜配置されています.
大きな構造としては,柱と梁,そして貫という日本古来の建築構造を現代的に解釈しています.EXPOという場所でそのDNAを展示しているわけですね.

東京の山手線.あるいはウィーンのリンク.またはパリのペリフェリック.多くの都市には「環状線」の役目を果たす交通網が存在しています.このリングは,EXPOという都市の環状線.しかも,高架(屋上)のある都市高速のような構造になっています.

大屋根リングの上からのEXPO会場です.歩いて一周2キロ.歩いて30分くらいでしょうか.
中世から現代の都市には,特にヨーロッパなどでは中心部に高い塔(教会など)を配置し,都心を主張する計画が主流でした.
ここでは,脱中心(実際真ん中は公園や森のような空間で占められています)つまり,脱20世紀的価値観が見え隠れします.周辺こそが交流の生まれる場所である,というと言いすぎでしょうか.

これはサウジアラビアのパビリオン.設計は,Apple の本社屋を手掛けた イギリスのフォスター&パートナーズ.分散された小さな建物が集まって全体が構成されています.中に入ると路地に迷い込んだかのような体験ができます.

イタリア館.今回の海外パビリオンで一番人気のようです.入場するのに4時間待つ人もいるとか... 設計は「未来は過去への旅」を記しサステナビリティを考える地元の建築家 マリオ・クチネッラ.

秋にはデザインカレッジの学生がデザインしたパッケージのコーヒー関連商品がディスプレイされることになるインドネシア館は,踊りあり,映像あり,温室あり,のダイナミックさが国の勢いを感じさせます.
さて,ページも限られているので,他の各パビリオンについては建築専門サイトのまとめをご覧ください.

ミャクミャクはもうみなさんご存じだと思います.では「こみゃく」はご存じですか?
EXPOがスタートして,一気に人気が出てきているのが,写真にあるような目の付いたキャラクター.当初は,全体システムの中で「ID」という公式名称があったものが,一般の人たちが「こみゃく」と呼びはじめ,SNSで人気に火が付いたようです.それで,公式もこの「こみゃく」というのを愛称として公式に採用したという経緯があるそうです.
これは普通に聞けば笑い話ですが,じつは現代の「デザイン」を考えるうえで重要なポイントが潜んだエピソードなのです.
今回のEXPOのデザインシステムをディレクションしているのは,デザイナーの 引地耕太さん.
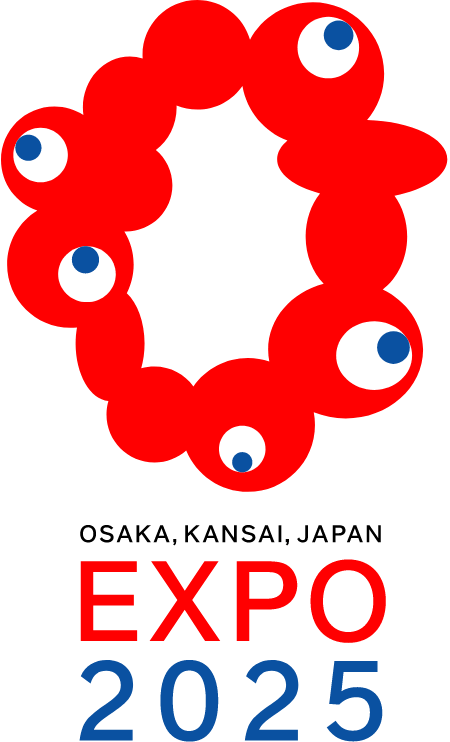
ご存じかも知れませんが,今回のEXPOでは,まずロゴが決まりました(左)
その後,このロゴを受けて,ミャクミャクというキャラクターが生まれ,全体のデザインシステムも並行して進められたそうです.
それぞれ別のデザイナーやクリエイターが関わりながら,ここまで統一感のある,かつ 現代的なオープンさをもってまとめられているのは,サインやロゴのデザインが,単体として優れているだけでなく,それらの背後にある思想(テーマ性)を軸にした「システム:しくみ」のデザインに落とし込まれているから,なんですね.
ここに,引地さんが率いている全体のデザインシステムがまとめられています.
このようなデザインシステム(ルールのようなもの)に則って,皆さんご存じの通りいろんなグッズが生まれてきています.
グッズにするときには,公式なロゴなどの活用ルールブックに則って制作しなければなりません.
もちろんグッズ制作以外にも,多くの人が関わるイベントでは,このようなルールブックが必ず存在します.

ただ,面白いのは「こみゃく」のように,派生的に2次創作とかファンアートのような動きも,公式がおおらかに受け止めて,一般の人々の創作を認めながら,大きな波を作っている点にあります.このような動きについて一般的に「オープンソース」と呼ばれるような思考があります.制限より自由を,そのほうが認知の広がりや最終的には経済的な施以降にもつながるという現代的な思考です.
こみゃくファンアート本当は,テクノロジーや映像,ランドスケープとか,いろんな視点でもっともっと語りたいのですが,とりあえず誌面が尽きたのでいったんはこのあたりでレポート終わりにします.
万博って,イベント!楽しい!ということが先行しがちですが,その背後にあるクリエイターやデザイナー,プランナー,つまり,企画側の思想を知ることで,より楽しみ方も増えると思います!
これから行かれる方はぜひ,いろんな視点で万博をお楽しみください:)